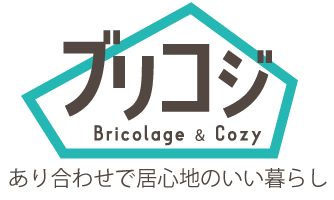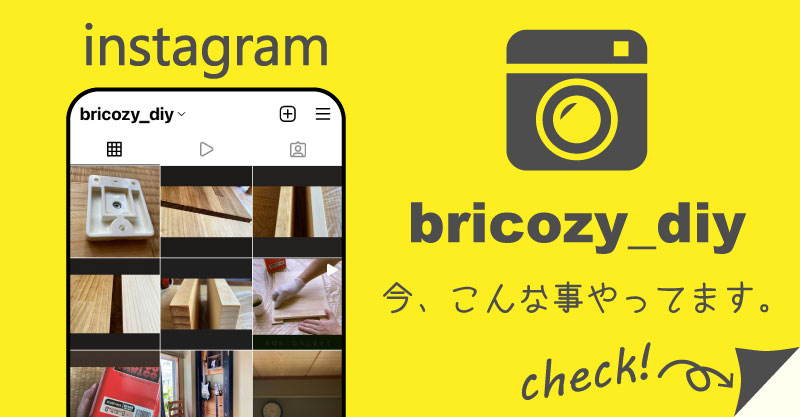お友達の影響で、自分からピアノを始めたいと言ったのに、始めてからわずか3ヶ月で辞めたいと言い出した。これって辞めさせるべき?
なかなか判断の難しいところですよね。
辞めさせるのは簡単ですけど、親として心配なのは
これだと今後、何をやらせてもすぐに辞めたいと言い出すのでは?
これが一番心配ですよね。
子供の頃の習い事ならまだしも、将来大学に行ったり、就職した際にも

「辞めてきたから」
なんて言われた日にゃあ、たまったもんじゃないですよね。
でも安心してください。
子供の内の習い事は『回路を開くこと』が重要なので、一つのことにつらい思いをさせてまで打ち込ませることにあまり意味はありません。
小さな頃から歯を食いしばって耐え抜いた結果、一流のアスリートになった選手の話が華々しく語られるせいで、ついつい同じことを自分の子供にも強いてしまいそうですが、
幼少期からのスポ根教育については必ずしも「良し」とされているわけではないんですよ。
テニスの伊達公子選手を始めとするトップアスリートを指導した小浦猛志先生によると、幼少期からテニスだけを教えると14歳頃で伸び悩むそうです。
それは基本的な身体機能を育てる時期に同じ運動しかやってこなかったことが原因の一つだと考えられています。
幼少期は一つの事を無理強いしてやらせるよりも、色んな経験をさせてあげる方が子どもの本当の意味での成長につながると言えますね。
でも、せっかく親子や両親で話し合って始めた習い事ですからせっかくであれば、楽しんで長く続けてほしいですよね。
なかなか難しい『幼児期の習い事の始め方』は以下のステップを参考にしてみてください。
習い事に関しては子供の根気の問題もありますが、案外、親の方が送り迎えなどの時間や体力を削がれて嫌になってしまうケースも少なくありません。そんなことで子供の将来性を狭めてしまわないよう、任せられる家事はプロに任せてしまうという手段もあります。
私自身はDIYが好きだし、片付けも頭の体操になるので休みの日はもっぱら子どもの相手の隙間をみてはちょこちょこ断捨離したり、部屋の模様替えをしたりしてますが、 まぁ進まない進まない。子どもが二人とも小さいっていうのもあるんでし[…]
STEP1 始めは超ゆっくり、超カンタンなことから始める

全てのことに共通することですが、最も基本となる動作をこれでもかというぐらいゆっくり、丁寧に教えることが大事です。
なぜなら子供は「言わなくてもついてはわかるようなこと」がわかっていなかったりするからです。
- ピアノであれば指一本で、順番に、鍵盤を押していくと、音楽に聴こえる。
- サッカーであれば足のどの位置でボールに触れるのかを手取り足取り確認する。
まるでタイムスリップでやってきた原始人に教えるつもりでやってみてください。
というのも私もその昔、学生時代にベースにハマっていたことがあってたくさん練習しました。
その中で特に大事だったのが『指の動かし方』でした。
バンドやロックの世界は独学者の多い世界ですから、とにかく変な指の動かし方、弾き方の人間が多い。
そういう人は遅かれ早かれ『弾けない限界』に出くわして楽器を弾くこと自体を辞めてしまいます。
しかしそこから抜け出して学校の中で、地域の中で、ライブハウス界隈で、業界で一目置かれる人というのはとにかく基本を大事にします。
勉強でも同じことが言えて、数学で伸び悩む人は方程式の『x』の書き方がそもそもおかしいことが原因だったりします。
自分の書いた文字がパッと見で、『x』なのか『)(』なのか『×』なのかが判断できないような文字を書いているせいで、計算に揺らぎや間違いが生じるそうです。
STEP2 超カンタンに『終わる』ことを1つクリアする
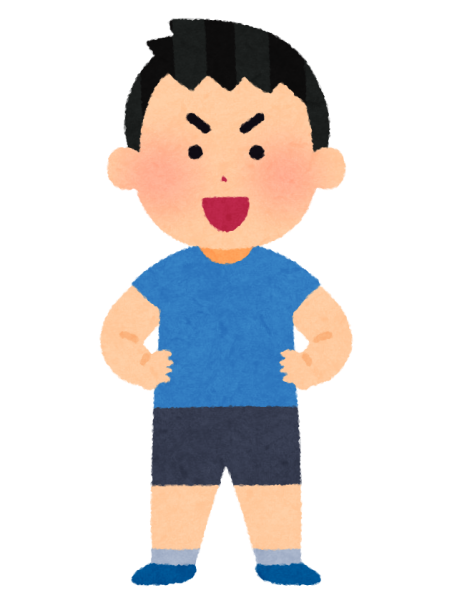
「そんなのカンタンだよ!」
子供がそんな感じで乗ってきたら今度は『少しだけ難しい課題』を用意します。

「おっ♩じゃあこれは?」
簡単なことばかりではすぐに飽きますし、難し過ぎれば辞めてしまいます。
『達成』と『ちょっとだけ難しい』のループを無理なく続けていける楽しい仕掛けをうまいこと作れるかが、大人側の腕の見せどころですね。
子供を習い事に通わせることの本当のメリット

同年代の自分より優れている子のやり方を間近で見られる
これが習い事の最大のメリットです。
すごい大人の一流のやり方って、同じ大人が見ても「いやー、こんなんできないわ」って引いちゃうじゃないですか?
子供でも同じでやっぱり同年代の子がうまくできてる方が刺激になるし、参考になるんですね。
ここで注意なのが1つ。
「〇〇ちゃんは上手くできてるんだから、〇〇ちゃんみたいにうまくやってごらん」はNGワード。
子供は他の子と比較するのが一番伸びないみたいです。
競争させるのも、やり方を真似るのもいいことですが、上から目線に立つのはやめましょう。

「これどーやってやるの?」
「んー、どーやるんだろうね。〇〇ちゃんはどうやってた?」
ここから先、他の子を観察したり、やり方を真似たりするのは本人次第。
肝心なのは習い事が上手くなることではなく、できないことにつまづいた時に自分でどう対処するかを学ぶことです。
『同じ課題に取り組んでる他者から学ぶというやり方もある』という感覚が得られる事が習い事の最大のメリットですね。
子供の習い事はいつまで続けたらいい?
ある程度の基礎的な動きと、課題への達成感を味わった後は辞めていい、というのが私の考えです。
一番難しいテイクオフの部分を軌道に乗せているのに自分でやり始めなかったらもう十分と思えばいいです。
なぜなら、物事が上手くなるには本人の『楽しい』がなければ続かないからです。
続かなければ上手くなるために必要な量の時間、よく言う『1万時間の法則』ってやつですね。
これに達しませんから上手くなりません。
そして、その楽しいと感じる感情は達成感からもたらされます。
簡単なことでもできるようになれば達成感は味わえているはずなので、その味をもう一度味わいたいか、もうお腹いっぱいかは本人が決めること。
いくら親が「大きくなってほしい」からといって、お腹がいっぱいな子供の口にご飯を詰め込むようなことは馬鹿げてますし、普通はやりたくないですからね。
4歳頃の子供の習い事をうまく軌道に乗せる始め方 まとめ
- 大人の感覚で端折らずに、基本の動作からスローモーションのようにゆっくり丁寧に確認する
- 達成感を得るために、すごく簡単なハードルをクリアする
【つまづいた時】
同年代の出来る子のやり方を見せる
【辞め時】
基本動作に慣れ、ある程度形になれば幼少期の習い事としては充分。 いつ辞めてもOK。
こうやって色々な経験をさせて、子供の回路を開いておけば、あとは何かが好きになった時に勝手に芽が出始めるはずです。
ゴリゴリのロックミュージシャンの中でも、作曲センスの高い人の中には、子供の頃にピアノを習っていた人がけっこう多かったりしますよね。
回路を開いておくとはそういうことです。
それを使うかどうかは本人次第。
親は子供にたくさんの経験をさせてあげてるだけで充分です。
親も子供もツライと思っているのに無理やり習い事を続けなくてもいいんですよ。